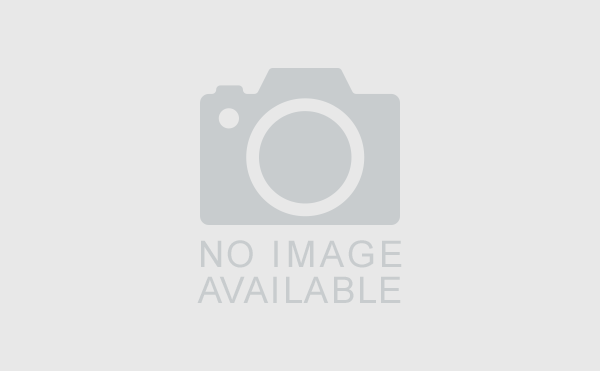体の構造とテコ
モーメントの話からつながってきますが、ほぼ全ての関節はテコの原理で筋肉に動かされています。
そのため、例えば軽い物を持っているつもりでも骨格や筋肉には大きなストレスになる場合があります。
もう少し詳しく話をしましょう。まずはテコの原理から。
下図のようなシーソーを考えると、支点から作用点までの距離がポイントとなってきます。
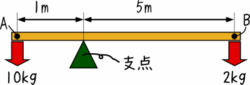
Aでのモーメントは10kg×1m=10kgm、Bのモーメントは2kg×5m=10kgm
なので支点周りのモーメントは同じになりますよね。
同じ=回転しないということです。
つまりBに2kgの力を加えただけでAに置いた10kgのモノが支えられるということを意味します。このときBの力を2kgより少し大きくしてやると10kgのAが持ち上がるわけです。
軽い力で重いモノを動かせるというと魔法のような話ですね。
でも、実はちゃんと代償を支払っています。それは“移動量”です。
たとえばAを10cm高く上げようとするとBは約50cm下に下がらなければなりません。
沢山動いても相手は少ししか移動しないわけです。
逆にAの方はBに置いた2kgのモノを持ち上げるのに10kgの力をかける必要がありますがかわりに10cm動くだけでBは約50cmも動いてくれるわけです。
さて、体の話に戻ると筋肉のほとんどは後者の立場を取っています。
少ない筋肉の収縮で大きな動きを実現するための工夫ですね。
このおかげで人間は手足を大きく動かすことが出来ます。
でも、逆に言うと筋肉はすごく大きな力を出しているということです。
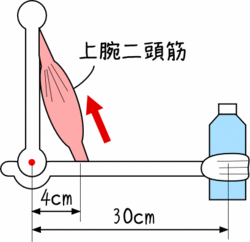 たとえば、右図のように肘を曲げて手に500ml(約500g)のペットボトルと持ったとすると上腕二頭筋は4kg弱の力を出して頑張っているという計算になります(上腕の重さを無視してます。それも入れるともっと大きな力になる)
たとえば、右図のように肘を曲げて手に500ml(約500g)のペットボトルと持ったとすると上腕二頭筋は4kg弱の力を出して頑張っているという計算になります(上腕の重さを無視してます。それも入れるともっと大きな力になる)
同じようにして計算してけばペットボトルから遠く離れたところ(肩や腰)の筋肉は腕の重さなども加わってさらに大きな筋力を出さなければなりません。
ですので最初に書いたように、軽いつもりでも持ち方次第では体に大きなストレスがかかります。
重い物を持つときはなおさらで、実際に持つ物の重さよりも何倍も大きな力(正確にはモーメント)が肩や腰にかかると思っておかなければなりません。
そすると、カラダに優しい物の持ち方というのも段々と見えてきますよね。