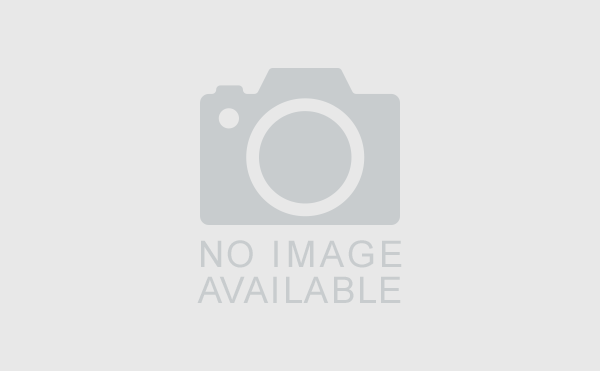コンテストではなくラリーなのだ
昨日は久しぶりにテレビの前に2時間すわって番組を見てました。
DVDで映画とかは見るけどテレビ番組自体はニュースぐらいしか見ない人なので。
もちろん見ていたのは鳥人間コンテスト。
滑空機は500mまでもう少し。これは本当にすごい。
プロペラ付けても1km前後しか飛べないチームが多いですから...
タイムトライアルは他のチームがもっと頑張ってくれないと競技として成立してないですね(笑)昨年に続きゴールしたのが1機だけってねぇ...
ディスタンス部門は気象条件の影響が大きかったようです。
で、これを見ていて鳥人間コンテストの英語名の由来を思い出しました。
学生の頃に読売テレビのディレクターの方から聞いた話です。
英語名は「JAPAN INTERNATIONAL BIRDMAN RALLY」
ここでのポイントは"RALLY"という単語で、モータスポーツのラリーをイメージしているそうです。
つまりサーキットのようなきれいな路面(=よい気象条件を待つ)で競い合うのではなく、ラリーのようにその時々で刻々と変わる路面(気象条件)で競い合うものだという思いが込められているわけです。
なので、風が吹くのは当たり前、一旦プラットフォームまで登ってきたらその時その場で与えられた条件でどこまで最高のパフォーマンスを発揮できるか。
「一年間一生懸命頑張った」、「破れない約束がある」、「だからもっと良い条件で飛びたい」...といった人の自分勝手な都合など自然には関係ないのです。
自然が時に女神に、時に悪魔になるわけですね。
厳しいけど、そこにドラマが生まれ競技自体を面白いものにするのでしょうね。
あ、人生もサーキットの中よりラリーの方が面白そうですね。