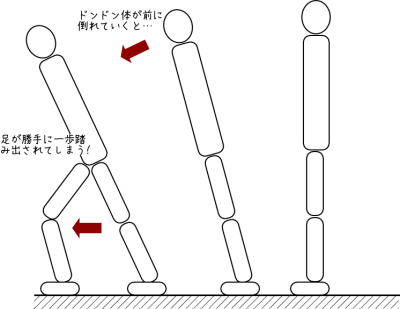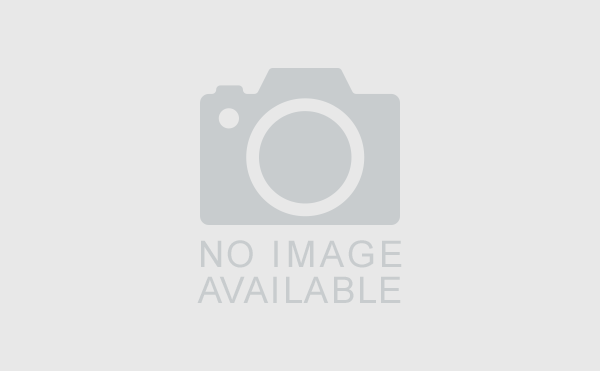2軸走法!?のつづき
昨日、2軸走法についてみっちりと(?)レッスンを受けてコツを教わってきました。
とはいえ、2軸っていう言葉はほとんど出て来ませんでしたけどね(笑)
2軸というのはわかりやすくイメージしてもらう為の言葉なだけでその人の感じ方によっていろいろな表現の仕方があるのだとおもいます。
さて、前回は地球の重力を使うなんていう小難しいことを書きましたが要はたっぷりある(笑)体重をもっと前に進むことに積極的に利用しましょうってことです。
具体的には体が前へ倒れていくと反射的に足が前に出るという現象を利用します。
気をつけの姿勢から体をドンドンと前に倒して行くといつか限界の角度に到達します。
そしてそこを超えてさらに前傾していき「もうあかん」となったときにどちらかの片方の足が勝手に一歩踏み出しますよね。
実はこの動きは体が反射的に行う動き(脊髄反射)で脳からの指令ではありません。
いちいち脳から命令を出していてはタイムラグが大きすぎてこけてしまいます。
なのでそうならないように脊髄にちゃんとプログラムされている動きなのです。
いってみれば本能で動かしているので本当に必要最小限の筋肉しか使われないのです。
で、このこけそうになって足を前に出すという動きを左右交互に連続してやっていくと自分ではまったく頑張っているつもりはないのに自然に前に進んでいきます。
ただ、このままだとドンドン前につんのめってこけてしまいます。
そこで、上半身のポジションをうまく調整してスピードを調整する。
これが2軸の走り方の本質的なところですね。
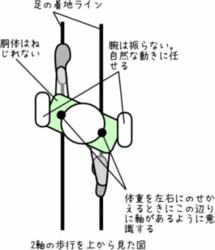 意識するのは上半身のポジションのみ、足は勝手に動くのでそれに任せるだけです。
意識するのは上半身のポジションのみ、足は勝手に動くのでそれに任せるだけです。
この動きを外から見ると右の図のように体の股関節付近を通る2本のラインにそって足をのせていく動きになります。また、体も全くねじれません。
足を2本のラインに交互に載せるときの重心移動の感覚を、中心に軸を作るというイメージに対して2軸と呼んでいるのです。
でも実際にはブレのない中心軸もやはり必要でそういう意味では3軸のような気もしないではないですけどね…
今回は絵を描くだけで力尽きたので詳しくはつづくということで。