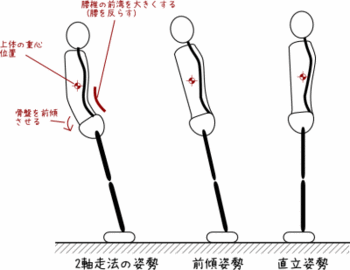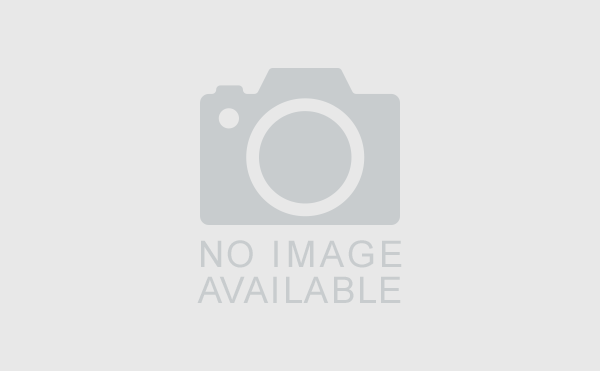2軸走法!?つづきのつづき
今日は朝から3kmスイム練習してきました。
あまり調子よい感覚はないのですが、タイム的には8月頃と比べると一つレベルが上がった感じです。泳ぎを変えたことが体に完全にインプットされたのかな?
さて、前回の続き。
前傾すれば足は勝手に前に出るとはいったもののず~っと前傾っていうのはちょっとありえませんよね。そんな走り方している選手もいませんし。
上体はまっすぐに起こしながらなおかつ重心は前に…
そんな矛盾してることができるのか?
ポイントは骨盤と背骨の角度をうまく調整してあげるということのようです。
頭のなかのイメージは下図のような感じ。
ただ、この姿勢をずっと維持するのはしんどいし格好悪い(笑)
なので、最初はこの姿勢からスタートして走りながら徐々に自分にとってリラックスできる姿勢を探していくという作業が必要になります。
僕自身も今その位置を模索中ですが、たまにすごく走りやすい時があります。
これはしばらく探しながら走り込むしかないのでしょうね。
あと、ポイントとして教えてもらったことは肩甲骨から腕にかけての脱力です。
これがまた僕にとっては難しい。ついつい力が入ってしまいます。
普段はあまり気づかない方が多いかもしれませんが、股関節と肩甲骨の動きというのは実は連動しています。特に対角線上に影響し合う場合が多いです。
右肩なら左股関節という感じで互いに影響し合っており、どちらかがうまく動かないともう一方の動きも悪くなります。
実際に整体で患者さんを見ていても肩が悪い人で股関節の動きが悪い人は多いです。
さて、話は戻って走る時にも肩甲骨の動きが非常に重要になってくるのです。
肩が力んでいると股関節がスムーズに動きませんからね。
ではどういう肩甲骨の使い方が良いのか?
それはズバリ
「力を抜いて体の自然な反射に身を任せる」
です。
勝手に足が前に出ればそれに合わせて勝手に肩も動くのです、それも最適な動きで。
なので脳みそから発する命令は
・重心位置を決める姿勢の維持
・体の脱力
の二つです。手足をどう動かそうなどということは考えない。
「走ることを考えずに走る」
これがこの走り方の奥義なのかもしれません。
ときどきうまく肩を脱力させ体の反応に任せるままに走れる時があります。
その時は確かに動きがなめらかな感じがあり、タイムも明らかによくなる事は確認しました。
ただ、それを維持できるように筋肉の動きを再プログラムするには少し時間がかかりそうです。
それと、うまくやらないと腰周辺の故障につながりそうな気も少ししました。
それについてはまた次回。
つづく。