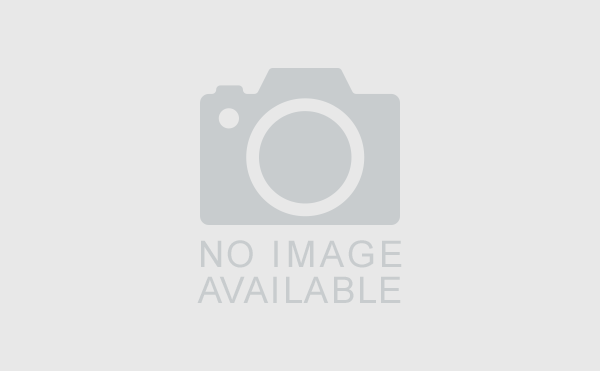赤身と白身とピンクの身~筋肉のお話
前回の続きです。
鮭の身の色がマグロほど赤くない(明るい赤っぽさ?)のは何故なのか?
実は知りません。鮮度の違いだったりして?
それと関係があるかどうかわかりませんが、筋繊維の種類は実はさらにいくつかのタイプに分けることが出来ます。
一般的には下記の3タイプでほとんどが占められます。
タイプ1(遅筋、赤筋)
タイプ2a(速筋、ピンク筋)
タイプ2b(速筋、白筋)
前回話をしていたのは「タイプ1」と「タイプ2b」の筋繊維のことです。
では、ここででてきた「タイプ2a」ですが、これはスピードも持久力もそこそこ兼ね備えたオールマイティな筋繊維といえます。そこで「赤」と「白」の中間ということで「ピンク筋」と呼ばれています。これが占める割合が多いと一番いいように感じますね。
ところで、前回書いたように一般的な筋では赤:白は1:1で、そこからの個人差は遺伝で決まってしまいます。今までの研究ではトレーニングなどによる赤→白や白→赤への筋肉の転換はヒトでは確認されていません。
「なんだ、遺伝で決まるのか」
と落胆する人がいるかもしれません。
しかし、速筋だけでいえばタイプ2a・タイプ2bの比率は、運動や環境によって大きく変化することが分かっています。
ですのでこの一番バランスの良い筋肉はトレーニング次第で比率を増やすことができるわけです。
ちなみにパワー競技系のアスリートの筋肉では実は「白筋」はほとんど見られず多くは「ピンク筋」です。「白筋」では繰り返しのトレーニングが素早い回復といった要求に応えられないからだと考えられています。
そういう意味でもピンク筋を鍛えればアスリートとしてパフォーマンスも良いと言えるのではないでしょうか?
と考えると鮭の切り身の色がマグロなどよりも明るめに感じるのは実は「ピンク筋」が多いのかもしれませんね。
川を上って行くには大きなパワーと持久力、その両方が要求されますから。
そんな、「ピンク筋」。実はダイエットにも関係が深かったりします。
それは次回に。