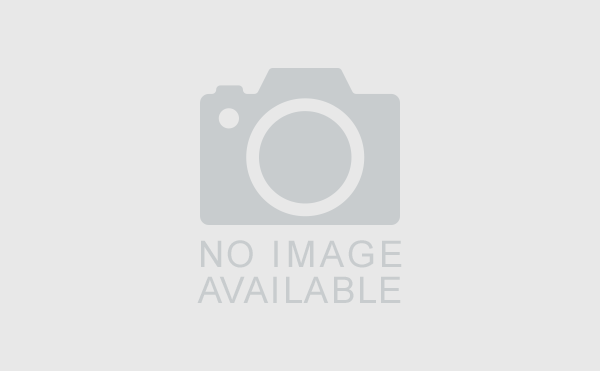薬食同源
またまた中医学ネタです。
よく「医食同源」っていう言葉使いますよね。
でも、実はこれは日本人の造語で本来中国では「薬食同源」というのだそうです。
「日本では医者が一番偉いからいつの間にかこうなってしまったんです」
とその漢方薬局の人はぼやいていました。
確かに意味をよく考えてみると
医療=食
ではなく、
薬=食
の方が合ってますよね。
これからは「薬食同源」で行きましょう!ってね。
さて、どうも中国人は「五」が好きなのか食べ物も内蔵も五種類に分類するのが好きなようです。
薬食同源→五味は五臓を養う
だそうですから。
で、五味について詳しく話を聞いてきました。
・甘味
気持ちや身体を弛める効果
モノ(エネルギー)を増やす効果
・酸味
“しめる”働き→筋肉を引き締めるなど
引き締めて不要なものを出し必要なものをとどめる
・苦味
熱・炎症をとるのに効果がある。
(冷やすというよりは移動させるというイメージ)
毒を外に出す働き(菊の花とかパセリとか)
・辛味
熱を生み出す、発散させる
(※身体に無理をさせることも)
・鹹味(かんみ、塩辛いという意味)
固いものを柔らかくする。水分を引き寄せる、取り込む
便秘などにもよい。
この考えに基づいて漢方薬は処方されているそうです。
例えば風邪薬の葛根湯の場合は
甘味→身体をほぐす(風邪で筋肉が張ることがありますよね)
苦味→熱を取る
という考えからこれらに分類される薬草などが含まれているそうです。
いままで漢方薬って適当(失礼)に薬草を混ぜ合わせてるだけかと思ったのですがちょっと認識が変わりました。
五味の分類が妥当かどうかという問題もありますが、長年の経験則による分類ですし今の栄養学的に考えても的外れではないように感じます。
中国四千年の歴史は奥深い!?