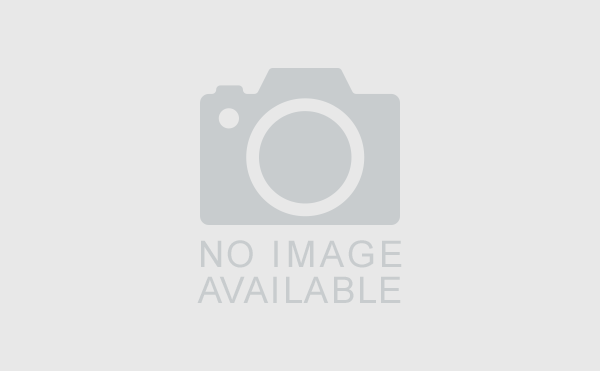太りやすい体質とは?
ピンク筋の話で脱共役タンパク質-3(UCP-3)というものが出て来ましたが“3”とあるからには他の番号もあるはず。
僕の知る限りではUCP-1~UCP-4まで発見されています。このなかでUCP-1というのは「褐色脂肪細胞」というものに多く含まれています。
通常の脂肪細胞(白色脂肪細胞)が取り込んだ脂肪として貯蔵するのに対して褐色脂肪細胞は脂肪を直接熱に変えて余剰なカロリーの消費と体温の維持という役割を担ってくれます。
じっとしていても脂肪を消費してくれる脂肪細胞...そう聞くととても魅力的ですよね。実際に、褐色脂肪細胞を活性化すればダイエットにいいという話もよく言われています。
冷たい物を触れば体温が下がったと勘違いし褐色脂肪細胞の活動が活発になるとか...
が、残念ながらその話はかなり怪しいです。
なぜならこの褐色脂肪細胞を沢山持つのは冬眠をする動物と乳幼児だけで、大人になると全脂肪細胞のうち1%程度にしか存在しないためです。
こんなにわずかでは活性化してもその効果のほどはどこまであるのか疑問です。
ちなみにその1%は何処に付いているのかというと首の後ろ、肩甲骨の下部、心臓の大動脈の周囲、腎臓の周囲だけです。
これから考えると体温が低下して厳しい状況になっても生きていくために絶対に必要な心臓を中心とした血液の循環系周辺はできるだけ体温を維持して活動できるようになっているようです。
人の身体ってよくできていますね。
で、大分前振りが長くなりましたが、近年私たちのカラダの脂肪の大部分を占める白色脂肪内にも同じような働きをするタンパク質(UCP-2)というものが発見されました。
つまり脂肪をため込むだけだと考えられていた白色脂肪細胞にも余剰の脂肪を熱に変えて脂肪の貯蔵量を調整する仕組みを備えている可能性があるのです。
このUPCがうまく働くかどうか、これを支配する遺伝子と太りやすい体質の間にひょっとすると何か関係があるかもしれません。これはこれからの研究しだい。
運動すると活性化するとか寒いところにいると活性化するとかそういう結果が出てくればまた誰かが新しいダイエット法を考え出すかもしれませんね。
ちなみにこれとは別に肥満に関わる遺伝子としてob遺伝子というものがすでに発見されています。そちらの方が肥満に関しては本命視されています。
これについては次回に。